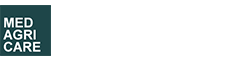認知症の方とのコミュニケーションで困らないためのポイントとは?
「何度も同じ話を繰り返されて、どう返答すればいいのかわからない」
「会話が噛み合わず、途中でどう接していいのかわからなくなる」
認知症の方とのコミュニケーションで、こうした悩みを抱える方は少なくありません。認知症の進行に伴い、記憶や理解力に変化が現れ、コミュニケーションを取ることが難しくなる場面があります。
本記事では、認知症の方とのコミュニケーションで心がけたい基本姿勢やポイント、よくある困った場面への対処法について解説します。
Contents
認知症の方とのコミュニケーションが難しい3つの理由

認知症の方とのコミュニケーションが難しいと感じるのは、主に認知症が脳に与える影響による3つの理由があるためです。それぞれについて詳しく解説します。
認知機能の低下による影響
認知症が進行すると、脳の情報処理能力が低下し、日常生活のさまざまな場面でコミュニケーションに支障をきたすことがあります。
例えば、新しい情報を覚えられず、直前の会話内容を忘れてしまうことが特徴的です。さらに、時間や場所、状況を認識する力が弱まることで、会話がかみ合わなくなるケースも見られます。
このように、認知機能の低下は、日常のコミュニケーションに深刻な影響を及ぼします。
認知症の方に見られる会話の特徴
断片的な記憶をもとに矛盾した発言をしたり、現実に合わない作話が見られることがあります。不安や混乱から感情が高ぶり、突然怒り出すといった行動も、認知症の特徴の一つです。
これらの特徴により、予期せぬ会話の展開が起こりやすく、対応に戸惑う場面が増えています。
認知症で変化するコミュニケーション能力
相手の言葉や指示を理解する力が低下するため、複雑な話を正確に受け取れなくなることがあります。また、会話の文脈や場の空気を把握する力が弱まり、不適切なタイミングでの発言や予想外の行動が見られる場合もあります。
こうした能力の変化は、会話の中での共感や意思疎通をより複雑なものにする要因です。
認知症の方とのコミュニケーションで心がけたい基本姿勢

認知症の方とのコミュニケーションでは、相手を理解し、信頼関係を築くために心がけたい基本的な姿勢があります。以下では、その具体的なポイントを解説します。
その人らしさを尊重する
認知症の方と接するときは、まず「その人らしさ」を大切にすることが大切です。
一人ひとりの価値観や性格には大きな違いがあります。これらを理解し、その人が持つ独自の背景に配慮することで、より良い関係を築くことができます。
どのような状況でも、ひとりの人間としての尊厳を守ることが、信頼関係を深める第一歩です。
共感する姿勢
相手の言動が理解しづらい場合でも、感情に寄り添い、共感することを意識しましょう。
言葉や行動に対して「正しい」「間違っている」と判断せず、相手の気持ちや不安に目を向けることが大切です。
共感の姿勢は、安心感を与えるだけでなく、認知症の方に「自分が受け入れられている」と感じてもらう大きな力になります。
安心感のある信頼関係
穏やかな態度や言葉遣いを心がけることは、相手に安心感を与える上で重要です。不安を感じると、混乱や感情の高ぶりが起きやすくなり、それが関係のこじれにつながることもあります。
相手が安心できる環境を整えることで、穏やかなコミュニケーションが生まれ、信頼関係を築く土台となります。
残存能力を活かす
認知症の方は、病気が進行しても「できること」が必ず残されています。
たとえば、日常の簡単な作業や趣味の一部など、自分でできることを続けることで、自己肯定感や自信を保つことができます。
できないことに目を向けるのではなく、残された能力を尊重し、それを活かすことを心がけましょう。
認知症の方との関係を深めるコミュニケーションのポイント

認知症の方との関係を深めるために、心がけたいコミュニケーションのポイントがあります。以下では、その具体的なポイントを解説します。
状況に応じた柔軟な対応
認知症の方は、その日の体調や気分によって反応が大きく変わることがあります。無理に決まった方法を押し通さず、その時々の状況に合わせて接し方を柔軟に変えることが大切です。
こちらのペースで進めるのではなく、相手のペースを意識して接することで、安心感を与えることができます。
非言語コミュニケーションの活用
視線や表情、相槌といった非言語的な要素は、認知症の方に安心感を与える大切な手段です。目線を合わせたり、穏やかな笑顔で接することで、親しみや信頼を感じてもらいやすくなります。
また、写真や絵などの過去の記憶に関係するアイテムを活用すれば、話題が広がるきっかけをつくることもできます。
わかりやすい話し方
認知症の方にとって、複雑な指示や早口の会話は理解が難しいことがあります。
短く簡潔な言葉を選び、ゆっくりとしたペースで話すことで、相手が内容を理解しやすくなります。また、1回に伝える情報を少なくすることも、効果的なコミュニケーションのポイントです。
傾聴をする
相手の話をしっかりと聞くことは、関係を深めるうえで欠かせません。
相づちや視線で、話を聞いているという姿勢を伝えることで、安心感を与えられます。話の内容が繰り返しや矛盾を含む場合でも、否定せず丁寧に耳を傾けることが大切です。
ポジティブな言葉がけ
認知症の方が安心して会話を楽しめるよう、褒める言葉や感謝の気持ちを積極的に伝えましょう。
些細なことでも「ありがとう」「すごいね」と声をかけることで、相手に自信と安心感を与えることができます。
よくある困った場面とその対処法

認知症の方との生活では、困った場面に直面することがあります。
こうした行動には、認知症の症状だけでなく、本人なりの理由や背景が関わっていることが多いです。そのため、対処法は人によって異なり、その日の気分や体調によっても効果が変わることがあります。無理をせず、できることから試してみましょう。
以下に、認知症の症状としてよくある状況と、その対処法について解説します。
徘徊
認知症の方が目的もなく歩き回る行動には、本人なりの理由や不安が影響している場合があります。
【対処法】
- 話を合わせながら気をそらす声掛けをしてみる。
「少し休憩してからにしましょう」など - 服や持ち物に名前を書くようにする。
- 徘徊予防センサーの活用。
- 近所の方に協力を求め、見かけた際には声をかけてもらう体制をつくる。
帰宅願望
自宅にいるにもかかわらず、「家に帰りたい」と言い出す場合があります。これは、環境の変化や不安からくることが多いです。
【対処法】
- 否定はせず、本人の話に合わせながら対応する。
「そうなんですね。どんな家ですか?」など - 環境の変化は最小限に抑える。
- 本人が覚えているものを近くに置くなどして安心できる環境をつくる。
- 近所の方に協力を求め、見かけた際には声をかけてもらう体制をつくる。
排泄の失敗
トイレの場所がわからなくなったり、間に合わなくなることがあります。
【対処法】
- トイレの場所がわかるように目立つ張り紙をつける。
- 定期的にトイレを促す。
- トイレの近くに部屋を配置する。
- 夜間でも行きやすいように、トイレまでの経路に照明をつける。
食事に関するトラブル
食べたことを忘れて、何度も食事を要求することがあります。
【対処法】
- 栄養やカロリー面で負担の少ないものを用意する。
- 違う作業を頼むなどして注意をそらす。
- 食事内容を記録する。
妄想や幻覚
物を盗られたと思い込んだり、実際にはない物が見えたりする場合があります。
【対処法】
- 否定はせずしっかりと傾聴する。
- 関連のない話をして、気持ちを他のことに向かわせる。
- 幻覚や幻聴が見られる場合は、そっと見守り、安心感を与える対応をする。
暴言や暴力
不安や焦りから、暴言や暴力が現れることがあります。
【対処法】
- 暴言に対して否定や対抗はせず、落ち着いた表情で話を聞く。
- 普段から安心できる環境をつくる。
- 暴力が始まった場合は、一時的にその場から離れ安全な距離を確保する。
- 家具の配置などを見直して、危険になるものは手の届かない場所にしまっておく。
まとめ

認知症の方とのコミュニケーションでは、相手を尊重し、安心感を与えることが大切です。基本的な姿勢や対応を心がけることで、困難な場面を乗り越え、信頼関係を築くことができます。
一方で、認知症の症状や行動に悩む場面があるときは、一人で抱え込まず、医師やケアマネジャーなどの専門家に一度相談することをおすすめします。
わたしたちアグリーグループでは、関東を中心に一都8県35箇所(2024年12月現在)で訪問診療所を展開しています。認知症の急激な変化でも、24時間365日対応が可能なため、お気軽にお問い合わせください。